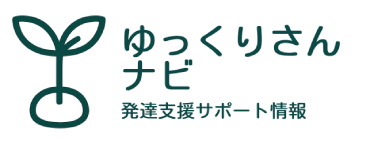🏥 小児科・専門クリニック
発達障害や知的障害のあるお子様の日常の健康管理と発達支援の入口となる医療機関について、利用方法から専門外来まで詳しくご紹介します。
👨⚕️小児科・専門クリニックとは?
発達障害や知的障害のある子どもにとって、かかりつけの小児科や専門クリニックは日常の健康管理と発達支援の入口となります。
一般的な小児科では風邪や発熱などの一般診療を行いつつ、必要に応じて発達外来・児童精神科・神経小児科などの専門医療機関に紹介する役割も持ちます。
特に発達障害の診断や薬物療法(ADHD治療薬など)は、専門クリニックや大学病院の発達外来で対応することが多いです。
👉 身近な「かかりつけ医」と「専門医」の両輪で支えていくのが理想です。
🏥かかりつけ小児科
日常的な体調管理、発熱・感染症対応を依頼できる。必要に応じて専門医療機関を紹介してもらう。
🧠発達外来
発達障害の診断、発達検査、薬物療法(ADHD治療薬など)を専門的に行う。
🧩児童精神科
精神的な発達課題や行動面の問題について専門的な診断と治療を行う。
⚕️神経小児科
脳や神経系の発達課題について専門的な診断と治療を行う。
📋 利用までの流れ
1
かかりつけ小児科を持つ
日常的な体調管理、発熱・感染症対応を依頼できる。必要に応じて専門医療機関を紹介してもらう
2
発達の不安を相談
言葉の遅れ、落ち着きのなさ、感覚過敏などを伝える。小児科で一次評価を受け、専門クリニック紹介に進むこともある
3
専門クリニック・発達外来での診断
臨床心理士や医師による発達検査や問診を受ける。必要に応じて薬物療法や専門的なリハビリに繋がる
4
継続的なフォローアップ
成長段階ごとに診察を受け、学校や療育先と連携していく
🔍 情報収集の方法
- 自治体の医療機関一覧
子育て支援ページに「小児科一覧」「発達外来案内」がある場合が多い - 日本小児科学会 医療機関検索
全国の小児科医を検索できる - 地域の発達障害者支援センター
医療機関や専門クリニックの情報を提供してくれる - 口コミ・親の会情報
「予約の取りやすさ」「先生の対応」などは実体験が大きな参考になる
📄 やっておくと便利な手続き・制度
- 自立支援医療(精神通院医療)
発達障害の診断・薬物療法を受ける際、通院費を軽減できる制度 - 医師の診断書の確保
受給者証申請や就学相談の際に必須となる - 母子手帳の記録整理
健診の記録や成長の経過が診断の参考資料になる - 紹介状の準備
大学病院や専門外来は紹介状が必要な場合が多いため、かかりつけで準備しておく
💡 保護者が知っておくと楽になるポイント
- 発達外来や専門クリニックは予約が数ヶ月待ちになることが多いので、早めの予約が肝心
- かかりつけ小児科を通して紹介を受けるとスムーズ
- ADHDなど薬物療法が必要な場合、処方できる医師が限られているため確認が必要
- 病院と療育施設・学校の「連携」が大切。診断書や意見書はコピーを取って保管しておくと便利
📚 参考リンク
- 日本小児科学会 医療機関検索
- 発達障害ナビポータル
- 各自治体の小児科・発達外来案内ページ